今日のテーマは
「最初のペンテコステのできごと」
1.どこで何が起こったか?
1.1 それは家の中で起こった
使徒言行録によれば、ペンテコステの日に
集まっていた人々が聖霊に満たされたのは、家の中でした。
彼らは家の中で座っていたと書いてあります。
突然、激しい風が吹いて来るような音が天から聞こえ、
彼らが座っていた家中に響いた(使徒言行録2章2節)
ということです。
家の中で座っていたところに、聖霊が注がれ
一同は聖霊に満たされ、“霊”が語らせるままに、
ほかの国々の言葉で話しだした(2章4節)のです。
要は家の中だったということです。
突然、激しい風が吹いて来るような音が聞こえましたが
それは彼らが座っていた家中に響いたのです。
1.2 おそらく120人が入れる広い2階の部屋だった
どのような家の、どのような部屋だったのでしょうか?
彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の部屋に上がった(1章13節)
と書いてありますから、おそらくその日も同じ部屋だったと考えられます。
人数は何人ぐらいだったでしょうか?
百二十人ほどの人々が一つになっていた。(1章15節)
と書いてありますから、おそらくその日も120人ほどだったと考えられます。
小学校の教室を2クラス分つなげれば、120人は入れるでしょう。
普通の8畳間とか20畳間とかでなく、その程度の広さがあったわけです。
そこでみんなが一斉に、いろいろな言葉で語りだしたのです。
1.3 多くの言語で神の偉大な業を語った
何種類ぐらいの言葉だったでしょうか?
9節から11節までに記されている地域を抜き出してみましょう。
数え上げると15の地域はあります。
| No. | 地域 |
|---|
| 1. | パルティア |
| 2. | メディア |
| 3. | エラム |
| 4. | メソポタミア |
| 5. | ユダヤ |
| 6. | カパドキア |
| 7. | ポントス |
| 8. | アジア |
| 9. | フリギア |
| 10. | パンフィリア |
| 11. | エジプト |
| 12. | キレネに接するリビア地方 |
| 13. | ローマ |
| 14. | クレタ |
| 15. | アラビア |
2.誰がどうなったのか?
2.1 人々がおそらく家の中ではなく家の周りに集まってきた
彼らがこれらの国々の言葉で語りだしたところ、
その物音に多くの人々が集まってきました。
この物音に大勢の人が集まって来た(2章5節)とあります。
まさか大勢の人が雪崩を打って、部屋の中に入ってきたのではないでしょう。
部屋の中には、すでに120人ほどが居たとすれば、
とても入り切れなかったでしょう。
もしこれが2階座敷で起こっていたということであれば、
大勢の人は、その2階座敷に集まったのではなく、
その家の周りに集まってきたと思われます。
2.2 おそらくペトロは家の中から外に向かって語った
そして家の周囲で、いわゆる家の外で驚いて語り合っていたのでしょう。
すると、ペトロは十一人と共に立って、声を張り上げ、話し始め(2章14節)
ます。2階座敷から、外にいる人々に向かって語りだしたのでしょう。
近くにいるなら声を張り上げる必要はありません。
外で大勢集まっていたなら、それらの人々全員に聞いてもらうために
声を張り上げなければならなかったでしょう。
人々は皆驚き、とまどい、「いったい、これはどういうことなのか」
と互いに言った。
しかし、「あの人たちは、新しいぶどう酒に酔っているのだ」と言って、
あざける者もいた。(2章12〜13節)
ということなので、集まってきた人々は、
口々に驚きの言葉を語っていましたから、うるさかったでしょう。
小声ではとても聞こえない状況だったと思います。
2.3 3千人ほどがイエスを信じて悔い改め洗礼を受けた
その日3000人が洗礼を受けて仲間に加わっていることを考えれば
相当多くの人々が、次から次へとやって来たに違いありません。
それらの人々はいったいどこで洗礼を受けていたのでしょうか?
ヨルダン川まで行くには、30kmは超えるのでおそらく違うでしょう。
ケデロンの谷は、どうでしょうか?
水が流れるのは冬の雨期だけということなので、ちょっと違いそうです。
それ以外で近場で水のある所となると、
北側のベトザタ(ベテスダ)の池か、南側のシロアムの池が考えられます。
もしかしたら、そういう場所で一斉に洗礼を受けていたのかもしれません。
3.その後どうなったか?
3.1 教会ができた
彼らは、使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、
祈ることに熱心であった。(2章42節)とあります。
使徒の教えとは、キリストの教え以外の何物でもありません。
キリストの教えを教え、交わりをなし、十字架を記念してパンを裂き
祈る、これはすなわち、現在の教会の姿そのものです。
ここで教会が始まっているのです。
すべてのものを共有し、財産や持ち物を売り必要に応じて分け合い、
毎日神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、
喜びと真心をもって一緒に食事をし、神を賛美していたのです。
3.2 不思議な業が起きた
すべての人に恐れが生じた。
使徒たちによって多くの不思議な業としるしが行われていたのである。
(2章43節)とあります。
不思議な業としるしが行われ、すべての人に恐れが生じます。
神が目の前で生きて働いておられることを、人々が認めざるを得ない
そういうことが次々と起きていったのです。
「美しい門」のところに置かれていた足の不自由な人が癒されたのも
その中の一つでした。民衆は我を忘れるほど非常に驚いたのです。
(3章10節、11節)
3.3 人数が増えた
ペトロの話を聞いて仲間に加わった人々は、どこに住んでいたでしょうか?
さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰って来た、
信心深いユダヤ人が住んでいたが、(2章5節)とあります。
ペトロたちキリストの弟子であった人々が、ガリラヤ出身であったのに対し
これらの人々は、エルサレムへの一時的滞在者ではありませんでした。
ギリシア語で
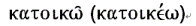
が使われていますので
「定住」していたと理解するのが良いでしょう。
もし一時的に、五旬節に合わせてエルサレムに来ていたとするなら
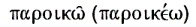
という言葉を使ったことでしょう。
これらの人々の出身地は上記の少なくとも15地域でしたが、
その後エルサレムに定住していた人々でした。
ですから、その後もエルサレム教会のメンバーとして留まれたのです。
さらに人々は増えていきます。
しかし、二人の語った言葉を聞いて信じた人は多く、
男の数が五千人ほどになった。(4章4節)とあります。
もしも一時滞在者ばかりであったら、エルサレムから自国に帰ってしまって
教会の人数は減っていたでしょう。しかしエルサレムに定住していたので
人数は減らず、三千人から五千人に増えていくのです。
むすび.
聖書をよく読んでいくと、当時のありさまが思い浮かべられると思います。
そうか、こんな感じだったのかもしれない。
完全にはわからなくても、およその姿が目に浮かんできます。
最初のペンテコステの出来事は、家の中の一室で起きました。
エルサレムのある家の、ある部屋の中で起きたことが、
今や世界中に広がっているのです。
そしてその聖霊の働きは、昔も今も変わらず同じなのです。
今も同じ聖霊が働いて、神のわざが起きているのです。
必要なことは、私たちが信じることだけです。
【今日の聖書】
使徒言行録 2章5〜6節
さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰って来た、
信心深いユダヤ人が住んでいたが、
この物音に大勢の人が集まって来た。
そして、だれもかれも、
自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、
あっけにとられてしまった。


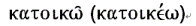 が使われていますので
が使われていますので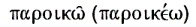 という言葉を使ったことでしょう。
という言葉を使ったことでしょう。